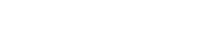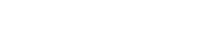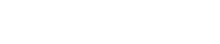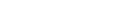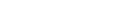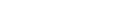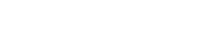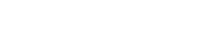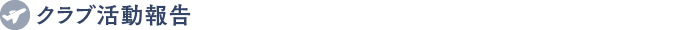第1回手作り紙飛行機コンテスト
第1回手作り紙飛行機コンテスト
出場レポート航空工学科
99年度卒業研究 (矢頭研究室)
■顧問 矢頭 祥夫
代表 松村 浩樹 紙本 拓也 駒月 雅治
1999年11月12日
『手作り紙飛行機コンテスト』とは
日本航空宇宙学会西部支部講演会の特別企画として、今回コンテストが開催されました。第1回なので下記の条件で和やかな雰囲気で行われました。
日時:11月5日(金)11時~17時
会場:長崎厚生年金会館
25m×4m×2.5m(高さ)
条件:発射は手投げ、無動力、材質は紙、会場内は無風
当日、2機持参(会場では製作しない)
スパン長の制限:両翼幅20cm以内
重量の下限制限:なし
結果:1位 19.09m 松村(日本文理大学)
2位 15.53m 竹山(長崎総合大学)
3位 15.32m 常屋教授(長崎総合大学)
以下 10m未満 約20名(九州大学教授、
九州大学大学院生など)
上記の結果を収めました。
7月中旬頃、矢頭研究室で卒業研究『無尾翼機の研究製作』を行っているとき、上記のコンテストを聞き、研究チームで話し合いをしました。当初は上記の条件は明記されておらず、今行っている研究の成果を発表する良い機会として、また、長島教授からコンテストについて詳しい話を聞いて、参加することにしました。
9月下旬に上記の条件が判明し、明らかに卒業研究とは異なると思いましたが、無尾翼機研究の一環として参考になると考え、また、卒業研究が行き詰った時に助言を得るためにつながりを持とうと考えたので資料を見直して設計を開始しました。
『製作過程を紹介します』
1.現在行っている研究「短形翼の無尾翼機」をそのまま単純に20cmにしてみたら、重心の位置が非常に不安定で、25m(目標)の飛行は難しいと考えました。
2.短形翼では最大揚力を発生する線(翼前縁より1/4の位置)を連ねる線が不足し縦安定が取りづらいので克服するため、大きめの後退角にして最大揚力を発生する線を長くし、翼端にねじれを加え縦安定を持たせました。
3.後退翼にすると、翼上面の流れが翼端に流れるのを防ぐために翼端にウイングレットをつけました。
4.重心の位置調整のために機体前方に錘を極わずかに取り付けた。
各種資料を参考にしながら10月の1ヶ月間、試行錯誤を繰り返し、卒研と同時進行しました。たまにチーム内で意見が合わず遅くまで議論した時もあります。
10月の下旬に体育館で、30mの飛行に成功して自身がつきましたが、次の日になるとまったく飛行しなくなり、飛行機の不安定と共に精神的にも不安になりました。果たして本番はどうなることかまったく分かりませんでした。
コンテストが始まり、練習が2投あり2投共まともに飛行距離が伸びずしかたないと諦めていましたが、本番は3投ある内の2投目に肩の力を抜いて軽くなげたら、19.05mの飛行に成功して思わずガッツポーズまで取ってしまいました。
今回のコンテストに参加して講演会に来ていた各界の教授とも知り合いになり、さまざまなことを聴いて参考になることがあり、目的以上のものが身についた。また、研究の参考となる教訓を多く得ました。
1.翼弦長の1/4~2/4の位置に重心を置く
2.斜め下に軽く投げ下ろす。
3.翼キャンバーを付け過ぎない。
この勢いを失わないように無尾翼の研究を成功させたいと思います。
(1999.11.12)